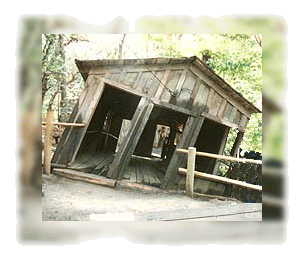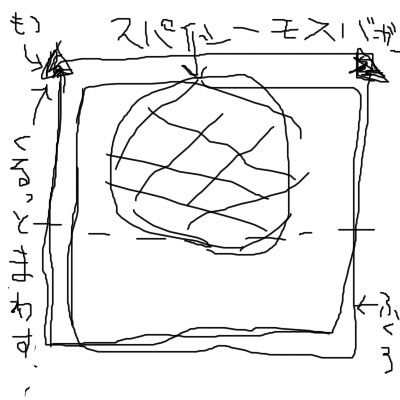1 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 01:32:08.19 ID:AcuGuC500
消しゴムを使うと消しゴムと消しカスに分かれるじゃん、
てことは消しゴムをいくら使っても消しゴムがなくなることはないと思うんだ。
分子レベルとかでもうこれ以上消しゴムと消しカスに分かれなれないってなったとして、
最後の分裂でも消しゴムは消しゴムと消しカスに分かれる。
消しゴムと消しカスに分かれなくなる=消しゴムを使い終わるだけど、そのとき消しゴムは存在しているから使い終わっていない。
つまり消しゴムを使い終わることはできない。
8 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 01:35:42.51 ID:EPOBUxMS0
カスはカスなんだよ
29 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 01:58:17.19 ID:l++fvNvh0
有限の空間を無限点に分割しようとするからパラドクスが発生する云々
78 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 02:53:51.24 ID:LC4rEKpE0
そういえば消しゴムを使いきったことないな
|
|
|
6 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 01:34:59.06 ID:2Ecbpe/20
砂山のパラドックス
http://ja.wikipedia.org/wiki/砂山のパラドックス
砂山から砂粒を個々に除去していくことを想定する。ここで、次のような前提から論証を構築する。
「砂山は膨大な数の砂粒からできている」(前提1)
「砂山から一粒の砂を取り除いても、それは依然として砂山のままである」(前提2)
前提2 を繰り返し適用したとき(つまり、毎回砂山の砂粒数は徐々に減っていく)、最終的に砂山の砂粒が一粒だけになる。前提2 が真であるなら、この状態も「砂山」だが、前提1 が真だとすれば、このような状態は「砂山」ではない。これが矛盾である。
このとき、このような結論を防ぐ方法がいくつか存在する。ある者は、砂粒の集積が砂山となること(あるいは、それを砂山と呼ぶこと)を否定することで第一の前提に反対する。またある者は、砂山から砂粒を1つ取り除いたとき、必ずしも砂山のままではないと主張することで第二の前提に反対する。さらに別の者は、一粒の砂であっても砂山と呼べると主張することで結果を肯定する。
23 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 01:50:39.90 ID:AcuGuC500
>>6
砂山から砂粒を取り除く
消しゴムを使用して消しカスを排出していく
たしかに似ています
が、砂山のパラドックスそのものではないと感じるのです
11 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 01:37:13.91 ID:URKh80Ai0
ゼノンのパラドックス思いだした
終わらないのは説明だとかって結論だっけ?
22 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 01:46:13.33 ID:AcuGuC500
>>11
詳しく教えてください
26 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 01:53:32.92 ID:URKh80Ai0
>>22
アキレス(人間)と亀が競争するって話なんだけど
そのまま競争したら、アキレスが有利すぎるので、亀はハンデとして、
いくらか進んだ位置からスタートする
んで、亀のスタート地点にアキレスが到達する頃には
亀はそれより少し進んだA地点まで進んでいて、
A地点にアキレスが到達する頃には
亀はそれより少し進んだB地点まで進んでいて、
B地点にアキレスが到達する頃には
亀はそれより少し進んだC地点まで進んでいて……
ってやっていくとアキレスは永遠に亀を抜かす事はできないっていうパラドックス
説明を無限にするから、抜かすまでの時間が無限になってしまうとか
そんな感じ

http://ja.wikipedia.org/wiki/ゼノンのパラドックス
30 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 01:58:34.06 ID:AcuGuC500
>>26
その題の場合時間は無限にありますが、消しゴムは無限に分裂しないと思うのです
179 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 05:01:24.26 ID:Ibdgkf5S0
ハゲ頭のパラドックス
数学的帰納法を意図的に誤用したジョークとして、次のようなものがある
髪の毛が一本もない人はハゲである。ハゲの人に髪の毛を一本足してもやっぱりハゲである。
よって数学的帰納法により、全ての人はハゲている。
以上のような論法の起源は、古代ギリシャの哲学者ミレトスのエウブリデス (en) が作ったとされるハゲ頭のパラドックス (Paradox of the Bald Man)に帰せられる。これは砂山のパラドックスの起源としても知られる。
前述のジョークにはさまざまなバリエーションがあるが、いずれも「少量の増加程度では大差ない。よって数学的帰納法より沢山の増加でも差はない」という誤謬を利用している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/ハゲ頭のパラドックス
32 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 02:00:29.44 ID:AcuGuC500
消しゴムを使い終わることはできないに対してどう思いますか?
あってますかそれともほかになにか答えがありそうですか?
42 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 02:08:33.05 ID:Y8tsjwNhO
>>32
消しゴムを使うと消しゴムと言う存在は消しカスへと変わる
つまり元は消しゴムだった消しカスと考えるなら使い切る事は無理であると言える
何故なら消しカスは練り消しとなり練り消しは無くならないからである
こうも考えられる
消しゴムは消しカスへと変わったのだからそれはもう消しカスと言う存在であり消しゴムではない
45 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 02:11:56.18 ID:AcuGuC500
>>42
うーん
もともと消しゴムだったのだから消しゴムとも言えるし
消しカスになったらそれはもう消しゴムでないとも言える…
38 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 02:07:18.97 ID:x+ScgEpy0
人が使えて初めて道具だ。 だから人が使えないレベルまで小さくなったのであれば、それはもう使い終わったと言える。
40 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 02:08:24.46 ID:AcuGuC500
>>38
使い終わって消しゴムが残っていても使い終わったと言えますか?
41 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 02:08:25.95 ID:Ffz1MY4a0
要は手に持って文字をこすって消すことができない大きさになっても消しゴムは残ってるって言いたいんだろ?
しかしだ、消しゴムとして使えない大きさになった時点でそいつは消しゴムとしての用途も意味も失っている
そのゴムを消しゴムと呼ぶのはちょっと惰性が過ぎやしないか
44 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 02:10:21.22 ID:AcuGuC500
>>41
なるほど
消しゴム本体を使用していくら小さくなっても消しゴムと呼ぶことに執着しすぎた感はあります
54 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 02:16:14.96 ID:qcx/Bq9t0
モノを消す性能がなくなった時点でそれは消しゴムじゃない
57 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 02:19:43.69 ID:AcuGuC500
>>54
つまり消しゴムを使っていく過程で消しゴムが消しゴムとしての機能を果たさなくなったとき、それは消しゴムでも消しカスでもない他の何かになるということか
56 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日:2011/10/16(日) 02:19:13.48 ID:RnUnSBUh0
ローレンツシュタイナーの原点をずらしたときのようなカオス理論で
消ゴムを使うことで消しカスが発生するが
消ゴムだと思っていたものは不定のある一点においてそれは共々消しカスと化す
61 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 02:23:38.37 ID:qcx/Bq9t0
そもそもそれが消しゴムか消しゴムでないかを認識するのは観測する人間のさじ加減ひとつなので
何処までが消しゴムか考える意味がない
55 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日:2011/10/16(日) 02:19:11.76 ID:1jXEbe7R0
「使う」のは「ゴムという物質」ではなく「消すという機能」
小さくなって「消すという機能」が失われた状態を「使いきった」と呼べるだろ
60 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 02:22:07.28 ID:Y8tsjwNhO
>>55
納得
59 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 02:22:00.05 ID:AcuGuC500
>>55
なるほど
使い終わるというのは物質的に最小になるのではなく、字を消すという消しゴムとしての機能がなくなることをいうのか
だから消しゴムを使い終わることができるのか!?
でもその機能がなくなる瞬間ってなんだろう
62 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 02:27:57.68 ID:Ffz1MY4a0
>>59
消しゴムは道具だからな
道具を使う主体にとって使用続行不可能になった瞬間だろ
小さくなりすぎたり手から滑ってどこかに行ってしまったり
66 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 02:33:36.86 ID:HhKWLk9E0
>>1
分裂じゃなく変化してんでしょ、だから元のはなくなるよ。
68 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 02:37:01.96 ID:AcuGuC500
>>66
全部消しカスになるか
どうしても最後の一粒が消しゴムから消しカスになるのがかんがえられない
71 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 02:40:49.68 ID:Y8tsjwNhO
>>68
確かに無理
ならそこが消しゴムの最後だろ
73 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 02:46:13.39 ID:Y8tsjwNhO
もういっその事こう考えてみた
消しゴムの仕事は書いた物を消す事じゃなく消しカスになる事
これは眠気から来た斬新な発想
75 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 02:48:27.93 ID:AcuGuC500
>>73
そのかんがえは消しゴムが字を消せなくなったとき消しゴムではなくなるということを回避できて
僕が突き止めたい最後の一粒の議論に持ってける気がします
76 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 02:52:03.37 ID:Y8tsjwNhO
>>75
回避じゃない
しかも消しカスになれる限界と文字を消せる限界は同時に訪れる
だから多分無意味
83 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 03:05:08.33 ID:AcuGuC500
10立方cmの消しゴム
一回消すと1立方cm消しカスになる
9回つかう
最後の一粒1立方cmが残る
見た目一緒
消しカス=消しゴム
\(^o^)/
84 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 03:08:00.83 ID:Y8tsjwNhO
>>83
いや待て
まだ折れるな
一回消しゴムを使うと消しカスが出る
逆に消しゴムを使わないと消しカスは出ない
見た目が一緒でも消しゴムから出てなかったならそれは消しカスではない
88 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 03:13:51.36 ID:AcuGuC500
>>84
消しゴムを使うってなんだろう
91 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 03:22:50.37 ID:DnS8uDVIi
(1)ちっちゃいモノを割る
ちっちゃいモノが半分になる
それが四分の一になる
それを何度も繰り返す
その物質が俺らから見えないくらいちっちゃくなる
(2)例えば、俺らがその物質と同等の大きさになるとする
だったら、割れないことは無いだろう
同じく、(1)を反復
これを無限に繰り返すと割れない物質は存在しないんじゃないか?
ってのを物理学者はどう解説するのか、是非聞いてみたい
この解釈だと、ヒトのサイズがちっちゃくなるにつれて、
消しカスは消しカスじゃなくなると思うんだ
115 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 03:46:49.48 ID:AcuGuC500
>>91
>この解釈だと、ヒトのサイズがちっちゃくなるにつれて、
>消しカスは消しカスじゃなくなると思うんだ
むむっ
それは消しカスをどう定義したのですか?
消しカスが消しカスじゃなくてなにになるのですか?
120 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 03:53:10.25 ID:DnS8uDVIi
>>115
例えば、その人がものすごく(もう、分子レベルまで)ちっちゃくなったとしたら
消しカスでも消しゴムとして使えるんじゃないか??
っていう解釈
141 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 04:08:27.44 ID:Ud+Mb3sg0
消しゴムは使っても必ず消しカスが出るとは限らない。
たとえば、黒鉛だけが付く場合もある。
それはそれで使ったといえるよね。
だから最後の一粒に黒鉛が付着した時点で終了。
147 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 04:14:45.96 ID:Y8tsjwNhO
>>141
確かに消しゴムを使った事にはなる
でも消しゴムからでたから消しカスだと思うんだ
121 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 03:53:30.11 ID:AcuGuC500
消しゴムは消しカスに変化してないとどうしても考えてしまいます
多分消しゴムと消しカスは黒鉛が付いている以外は物質的には同じだと思います
なので変化前変化後で考えると黒鉛の付着の有無…
摩擦による変形…
変質…
わからない
頭が足りないから大きさで考えるしかなくてどうしてもちぎれて消しカスができるという回路になってしまいます
難しい(>_<)
130 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 04:00:15.02 ID:9QlfeCOw0
>>121
考えるとか考えないとかどうでもいい 定義するのかしないのか
変化しないと定義するなら 消しカス=消しゴムだから消しゴムは使い終わらない
変化すると定義するなら 使い切る
165 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日:2011/10/16(日) 04:38:59.22 ID:TzlUXbtu0
原理
鉛筆で書いた線が消える原理は単純なものである。まず、鉛筆で書いた部分には黒鉛(鉛筆の芯の成分)が付着する。
消しゴムでこれをこすると、ゴムが紙に付着した黒鉛を剥がし取りながら、消しゴム本体より消しかすとして削れ落ちる。
更にその消しかすが紙から黒鉛を剥がし取りつつ包み込んで取り除く。紙からは完全に黒鉛が除去されて消しかすに移行し、
消しゴムには新しい表面が露出する。以上のサイクルで消しゴムが減り、消しかすが出て字が消える。
174 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 04:47:36.68 ID:ha1SqE5j0
>>165によれば、黒鉛を巻き込んだ消しゴムを消しカス、巻き込んでいない
のが消しゴム、で問題あるかな?
194 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 05:44:44.77 ID:+HWQ+6pg0
消しカスを集めたらねり消しになる=消しカスにも「消す機能」は備わっている
つまり消しゴムと消しカスにはどれ位汚れているかという差異しかなくぁwせdrftgyふじこlp
20 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 01:43:43.12 ID:URKh80Ai0
どっちみち使いきる前に無くなるのが消しゴムの運命
21 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2011/10/16(日) 01:45:52.55 ID:uZVZPtvz0
>>20が真理
習慣を変えると頭が良くなる―東大生が教える7つの学習習慣―
論理パラドクス―論証力を磨く99問
消しゴムBOX300個入り
関連記事
ちょっとだれか面白いパラドックス教えてくれ。
脳を使わなすぎて思考回路にぶくなってきた
落ちの難しい難解四コマを全力で解析するスレ
面白いパラドックス教えて
論理パラドクスでも解かない?
グーで勝ったら10万 チョキなら100万 パーなら1000万
難しい問題やパラドックスを教えろ
難問・奇問を出すと誰かが解決してくれるスレ
|
|